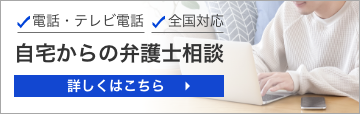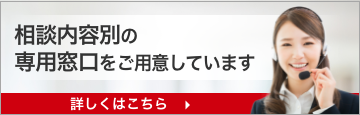カルテルと談合の違い|発生しやすいケースと独占禁止法の違反事例
- 一般企業法務
- カルテル
- 談合
- 違い

2020年の大阪府岸和田市の製造業事業所数(従業員4人以上)は302事業所で、年末従業員数は8632人となっています。
カルテルと入札談合は、いずれも独占禁止法(※)で禁止されている違法行為です。違反者には刑事罰・過料や課徴金納付のペナルティーが発生するため、各事業者はカルテルや入札談合の発生防止に努めましょう。(※正式名称:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
今回はカルテルと入札談合について、両者の違い・独占禁止法による規制内容・発生しやすい状況の例などを、ベリーベスト法律事務所 岸和田オフィスの弁護士が解説します。
出典:「製造業の状況」(岸和田市)
1、カルテルと入札談合の違いは?
カルテルと入札談合は、いずれも独占禁止法により「不当な取引制限」として禁止されています。
「不当な取引制限」は、以下のとおり定義されています。
⑥この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
(独占禁止法第2条第6項)
「カルテル」や「入札談合」は、独占禁止法上明確に定義されているわけではないものの、不当な取引制限に当たる行為は、カルテルや入札談合などに分類されると理解されています。
-
(1)カルテルとは?
「カルテル」とは、競争を回避するために本来事業者が自主的に決めるべき、商品やサービス等に関する以下の事項を、複数の事業者が共同で決める行為を意味します。
- 価格
- 販売数量
- 取引先
たとえば、市場シェアの大きい複数の事業者らがカルテルを形成し、商品の価格を高く設定してそれを維持すれば、消費者は当該商品を高い価格で購入せざるを得ません(価格カルテル)。
本来であれば市場原理が働き、価格競争を通じて適正な商品価格に落ち着くはずなのに、カルテルによって複数事業者が商品価格を高く維持しているため、消費者は当該商品を高値で購入せざるを得ず、消費者が不利益を被る結果となります。
同様に、カルテルによって販売数量や生産数量を絞った場合、商品やサービス等の市場への供給が減少するため、その結果として、これらの商品等の価格は高く維持されます(数量カルテル)。
この場合もやはり、カルテルの当事者である事業者が利益を得る一方で、消費者の利益が害されてしまいます。
このように、カルテルは市場競争の原理を排除して、消費者の犠牲の下に事業者が利益を得る行為であるため、不当な取引制限として禁止されているのです。 -
(2)入札談合とは?
「入札談合」とは、公共工事や公共調達などで入札が行われる際に、複数の事業者が事前に話し合って、受注予定事業者を決める行為を意味します。
入札談合においては当該受注予定者が実際に落札できるように入札価格を調整することが必要であるため、実質的に落札額にも影響を及ぼすことが多いです。
公共工事や公共調達などに関して入札制度が採用されている目的は、受発注のプロセスを透明化するとともに、市場競争の原理を働かせて発注金額を適正化する点にあります。
しかし入札談合が行われると、密室のやり取りで受注予定事業者が決まり、受発注プロセスの透明性が害されます。さらに、市場競争の原理が働きづらくなる結果、発注金額が不当に高額となってしまう可能性が高いです。
入札談合により事業者が利益を得る一方で、公共工事や公共調達の発注者である国や地方公共団体には経済的な損害が発生します。
国や地方公共団体の損害は、納税者である市民の損害に等しいため、入札談合は決して容認できる行為ではありません。
そのため入札談合は、カルテルと同様に不当な取引制限として禁止されています。
2、カルテル・入札談合に対するペナルティー
不当な取引制限に該当するカルテルや入札談合は、刑事罰・過料や課徴金納付命令の対象となります。
ただし課徴金については、公正取引委員会に対する報告や調査協力等を行うことにより、減免が認められることがあります。
-
(1)刑事罰・過料
独占禁止法に違反するカルテル、入札談合および関連している行為をした場合は、以下の刑事罰・過料の対象となります。
違反行為の内容 罰則条文 量刑等 - 不当な取引制限(未遂を含む)
独占禁止法第89条第1項第1号 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
※両罰規定により、法人・団体について5億円以下の罰金(同法第95条第1項第1号、第2項第1号)- 不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約の締結
- 確定した排除措置命令等に従わない行為
同法第90条第1号、第3号 2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
※確定した排除措置命令等に従わない行為については、両罰規定により、法人・団体について3億円以下の罰金(同法第95条第1項第2号、第2項第2号)
※国際的協定又は国際的契約の締結については、両罰規定により、法人・団体について300万円以下の罰金(同法第95条第1項第4号、第2項第4号)
※国際的協定または国際的契約の締結については、違反の計画を知りながら防止・是正に必要な措置を講じなかった法人代表者に対しても300万円以下の罰金(同法第95条の2)- 事件の調査に関する公正取引委員会による出頭命令、鑑定命令、物件提出命令への違反等(行政調査の拒否等)
- 事件の調査に関する公正取引委員会による検査の拒否、妨害、忌避
同法第94条 1年以下の懲役又は300万円以下の罰金
※両罰規定により、法人・団体について2億円以下の罰金(同法第95条第1項第3号、第2項第3号)- 公正取引委員会による出頭命令等への違反。一般調査の拒否等、事件の調査に関するものを除く
同法第94条の2 300万円以下の罰金
※両罰規定により、法人・団体について300万円以下の罰金(同法第95条第1項第4号、第2項第4号)- 排除措置命令違反(刑を科すべき場合を除く)
同法第97条 50万円以下の過料 - 裁判所による違反行為等の緊急停止命令への違反
同法第98条 30万円以下の過料 -
(2)課徴金納付命令
不当な取引制限に当たるカルテルまたは入札談合を行った事業者に対しては、公正取引委員会により、以下の式によって計算される課徴金の納付が命じられます(独占禁止法第7条の2)。
課徴金額=
違反期間中の対象商品・サービスの売上額or購入額×課徴金算定率+違反期間中の財産上の利益に相当する額
※不当な取引制限の場合、課徴金算定率は原則として10%です。ただし、違反事業者およびそのグループ会社がすべて一定の規模(同法7条の2で定める)の場合、課徴金算定率は4%となります。
※課徴金と罰金の双方が課(科)される場合には、罰金額の2分の1が課徴金から控除されます(同法第7条の7)。 -
(3)課徴金には減免制度あり
カルテル・入札談合に関する通報を促進し、不当な取引制限を抑制する観点から、違反事業者が公正取引委員会に対する報告・調査協力を行った場合、課徴金の減免が行われます。
減免される課徴金額は、申請順位や協力度合いなどによって、以下の要領で決定されます。
申請順位(申請の順番) 申請順位に応じた減免率 協力度合いに応じた減算率 調査開始日前の申請 1位 全額免除 - 2位 20% +最大40% 3位から5位 10% 6位以下 5% 調査開始日以後の申請 最大3社※ 10% +最大20% それ以降 5% ※調査開始前の申請と併せて5社まで
3、カルテル・入札談合が発生しやすい状況の例
独占禁止法違反のカルテルや入札談合は、特に以下のいずれかに該当する場合に発生するリスクが高いと考えられます。
どの事業者も、同じような商品・サービスを同じようなコストで提供している場合、事業者間で差別化を図る動機づけに乏しいため、カルテルや入札談合につながりやすい傾向にあります。
② 参入事業者が少ない
商品・サービスを提供する事業者の絶対数が少ない場合、カルテル・入札談合が容易になる傾向にあります。
③ 需要の価格弾力性が低い
少々価格を上げたとしても、商品やサービスの需要があまり減少しないと見込まれる場合には、カルテル・入札談合による価格のつり上げが行われやすい状況と言えます。
④ 新規参入が困難である
新規事業者の参入コストが大きい場合、カルテル・入札談合が打破されずに長期間継続する傾向にあります。
4、カルテル・入札談合の違反事例
公正取引委員会が公表している、カルテル・入札談合の違反事例を紹介します。
参考:「これまでにどんな事件があったの?~私たちの身近に起こった事件ファイル」(公正取引委員会)
-
(1)カルテルの違反事例
旅行業者5社がカルテルを形成し、中学校の修学旅行について、バス代・宿泊費・規格料金・添乗員費用の基準額を設けることに合意しました。
旅行代金に下限を設けるこのような合意は、不当な取引制限であるカルテルに当たるとして、公正取引委員会が旅行業者に対して排除措置命令を行いました。 -
(2)入札談合の違反事例
電気設備工事の競争入札において、参加事業者10社が事前に協議を行い、落札する事業者と落札価格を取り決めていました。
公正取引委員会は、上記の行為を不当な取引制限である入札談合に当たると判断し、排除措置命令と課徴金納付命令を行いました。
さらに、市役所の職員が関与した官製談合に当たると判断されたため、市役所に対する改善措置要求も併せて行われました。
5、まとめ
カルテルや入札談合は、事業者が市場原理を不当に排除し、市民の犠牲の下に利益を得る「不当な取引制限」として、独占禁止法で禁止されています。
事業者は、カルテルや入札談合に関与しないように十分注意し、万が一自社の関与が判明した場合には、速やかに公正取引委員会へ報告等を行いましょう。
ベリーベスト法律事務所は、独占禁止法に関する事業者からのご相談を随時受け付けております。カルテルや入札談合に関するチェック・アドバイスをご要望の場合は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています